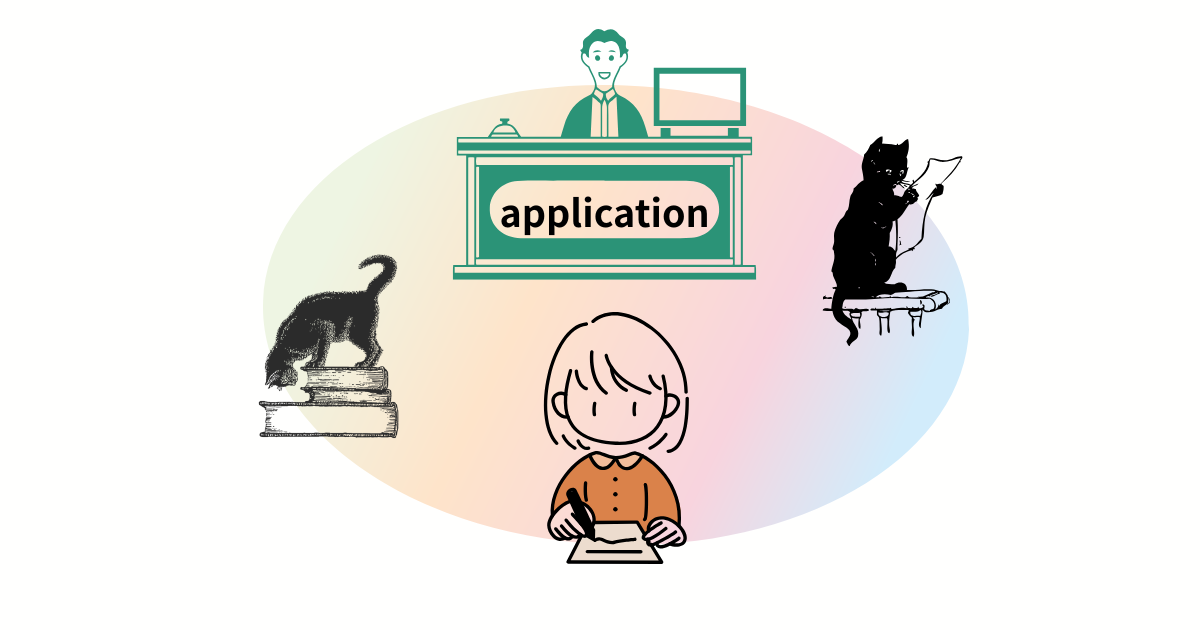ここでは、介護保険制度で利用できる制度のなかから、
<目次1>保険による介護サービスの利用を開始するための制度と、<目次2>活用したい介護保険サービスの負担を軽くする制度についてご紹介しましょう。
👉目次から必要な内容を選択してご覧ください!
保険による介護サービスの利用を開始するための制度👉
まずは介護保険のサービスが使えるようになる手順をご紹介します。
介護保険を使うためには条件が2種類あります。
1つ目が65歳以上で要支援・要介護認定を受けていること。
もう1つが40~64歳で※特定疾病を患っており、かつ要支援・要介護認定を受けていることです。両者ともに要介護・要支援認定を受けていなければなりません。
※特定疾病1.がん[がん末期]2.関節リウマチ3.筋萎縮性側索硬化症[ALS]4.後縦靱帯骨化症5.骨折を伴う骨粗鬆症6.初老期における認知症7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病[パーキンソン病関連疾患]8.脊髄小脳変性症9.脊柱管狭窄症10.早老症[ウェルナー症候群]11.多系統萎縮症12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症13.脳血管疾患14.閉塞性動脈硬化症15.慢性閉塞性肺疾患16.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険申請までの手順、要介護認定の受け方についての詳細はリンクを参照してください
介護保険サービスの種類について
介護保険サービスには「居宅介護支援サービス」「通所サービス」「訪問サービス」「短期入所サービス」「地域密着サービス」「施設入居サービス」「福祉用具の購入・レンタル」「住宅リフォーム」などの種類があります。
以下、ひとつずつ内容を見てみましょう。
居宅介護支援
居宅介護支援とは「ケアプラン」を作ったり、介護の悩み相談に対応したりする内容で在宅で介護保険サービスを利用する際にいちばん最初に関わるケアマネジャーのサービスです。
担当ケアマネの良しあしで介護サービスの内容、ひいては要介護者のその後の介護生活に大きな影響を与えます。
在宅介護の場合は、家族のストレスは大きくなりがちです。孤独になりがちな時に、信頼できるケアマネジャーに相談することは、心身ともに余裕を生み介護の継続が望めるものです。
はじめての利用の場合は、まずは自分の街の地域包括支援センターに相談に行くことをおすすめします。
訪問介護サービス
訪問介護サービスとは職員が介護対象者の自宅を訪問して、身体介護や生活介護を行うホームヘルパーによるサービスです。医療と連携して、医療的なチェックは行いますが、医療行為は出来ません。
定期にヘルパーが訪問することで、利用者は自宅で今まで通りの日常生活を継続することが可能になり、認知機能や生活機能を保つことができます。
また、家族のレスパイトとしてもホームヘルパーを上手に利用することで介護の負担軽減に大きな役割を果たします。
訪問看護
訪問看護とは、看護師や理学療法士、作業療法士などが自宅を訪問して生活機能の維持や改善。医師の指示による医療的なサポートをするサービスです。脈拍や体温などの計測、点滴や注射などの処置、褥瘡のケア、また簡易的なリハビリテーションを行います。
自分や家族では手が回らない医療的な側面まで見てくれるので、疾患のある人には必要と言えるでしょう。ただし、医師の指示書を必要とします。
訪問リハビリテーション
しっかりと機能訓練をして、機能の向上や現状維持を目指したい人におすすめなのが訪問リハビリテーションです。作業療法士や理学療法士などのリハビリのプロが自宅を訪問し、利用者に合わせて機能訓練を行います。
運動だけでなく、誤嚥予防に歯科医師と協働し、口腔機能を改善するリハビリにも対応できるのが魅力です。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
「昼も夜も、体調が不安定」「ひとりで生活している」「日中も看護が必要」など、24時間体制の見守りが必要な人へのサービスになります。
夜間対応型訪問介護
「夜だけ見守りがほしい」「夜間トイレ介助だけ頼みたい」など、日中は大丈夫だけど夜間に不安がある人に向いているサービス。
この二つについては、比較表にまとめてみました。
| 項目 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 夜間対応型訪問介護 |
|---|---|---|
| 📅 サービス時間帯 | 24時間対応(昼も夜も) | 夜間のみ(例:18時〜8時) |
| 🔄 巡回のタイプ | ・定期訪問+随時対応 ・ナースの訪問も可能(看護付き) | ・定時の訪問(見守り)+緊急時の対応 |
| 🚨 急な呼び出し | 随時コール対応あり(必要に応じて訪問) | 夜間のコール対応+必要なら訪問 |
| 👩⚕️ 医療的ケア | 看護職員が訪問できる(必要に応じて) | 基本は介護職員のみ |
| 💡 主な対象者 | ・ひとり暮らしの高齢者 ・介護度が重めの方 | ・夜間に不安がある方 ・見守りが必要な方 |
定期巡回は、平均10分〜20分の短時間の滞在時間で1日に複数回訪問します。1回の訪問滞在時間、1日の訪問回数は決められていません。また、24時間体制が整っており、緊急時・夜間・早朝の対応も可能です。
一方、訪問介護のサービス提供時間は最低でも30分以上は必要となります。訪問介護も状況によっては、1日に複数回利用が可能ですが、「2時間ルール」という制度(介護保険の不正防止目的で導入されたルール)があって、サービス利用の間隔を原則2時間以上空けないと、認められません。
また、訪問介護は地域の限定は無いのに比べ、上記二つは密着型サービスのため事業所と同じ地域に住居地がなくてはなりません。
料金設定も、訪問介護の場合は一回ごとの料金で、利用した分のみになりますが、上記二種のサービスについては月単位の料金となります。
対象者によってどちらを利用したほうが良いかは、医療者及び専門職とよくご相談ください。
居宅療養管理指導
医療的なケアが必要な人のために医師や看護師が自宅を訪問し、健康の診断や指導などがうけられます。往診と間違いやすいのですが、必要な時のみ訪問する往診と違って、居宅療法管理指導は定期に訪問するものです。体力の落ちた人におすすめのサービスです。
通所サービス(デイサービス・デイケア)
通所サービスとは自宅から施設に通うサービスです。施設に通うことで、機能維持や気持ちの活性化が図れ認知機能の向上が望めます。同時に家族の介護負担の軽減が期待できます。
通所サービスにはデイサービスとデイケアがあります。よく混同されやすいサービスですが、他者との交流を通して、認知症の予防や気持ちの活性化の目的には福祉系のデイサービス。リハビリや機能訓練による運動機能の維持向上を目的とするなら医療系のデイケアが良いでしょう。
地域密着型通所介護(小規模デイサービス)
定員が18名以下の小規模のデイサービスです。事業所と同じ地域に住所地を必要とする地域密着型サービスです。その地域で暮らす人しか利用できない小規模が特徴で、濃密な介護を受けられ、住み慣れた街でサービスを受けられるのが大きな魅力でしょう。
ただし、事業所と同地区(同保険者)に住居があることが必要です。
認知症対応型通所介護
認知症の人に特化したデイサービスです。認知症の人の対応に優れた専門職によって日常介護がなされるため、重度の認知症の人への最適な対応はもとより、認知機能の衰えを防止するうえでも非常に効果的な環境と言えます。地域密着型サービスになりますので事業所と同地区(同保険者)に住居があることが必要です。
短期入所生活介護(一般型ショートステイ)
短期入所型のサービスとは、普段は在宅介護をしている人が必要時、泊りのサービスを受けられるものです。家族のレスパイトに利用することも可能で、原則理由は問いません。ただし、連続利用は30日を限度とします。それを超えても利用する場合は、31日目を自費利用する方法や安心ショートなど、市町村の独自サービスを利用することができます。
各行政にサービスについては、ケアマネジャーや管轄の介護保険課にご確認ください。
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
ショートステイのなかでも医療的なケアが必要な人が利用するのが医療型ショートステイです。医療系の施設(介護老人保健施設)などに短期間だけ入居することで医師や看護師などのもと、安心して療養ができます。
ただし、内部の医師による診察が行われるため、利用の間は外部の病院を受診しにくくなります。事前に処方のことなどよく話を聞いておくことが大事です。
福祉用具のレンタル
在宅介護などの際に必要になる福祉用具は保険が適用されレンタルすることができます。ただし保険適用内の福祉用具は厚生労働省によって定められていますので事前に確認をしておきましょう。
保険適用内でレンタルできる福祉用具
- 車いす
- 車いす付属品
- 床ずれ防止用具
- 手すり
- 歩行器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置
- 特殊寝台(電動ベッド)
- 特殊寝台(電動ベッド)の付属品
- 体位変換器
- スロープ
- 歩行補助つえ
この中には、医師の意見書を要するものや、要介護度が限定されたものなどが含まれるため、ケアマネジャー及び専門職にご確認ください。
福祉用具の購入
購入の場合も必要と見なされれば介護保険が適用されます。購入には限度額がありますのでケアマネジャーなどに確認しましょう。
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分 など
住宅改修
介護が必要になった人にとってケガをするリスクがある個所については、保険適用で改修が可能です。段差や滑りやすい床などリフォームによってリスクを最小限にすることが重要です。申請については専門職が代行してくれますので、上限額を含め気になるところはまずはケアマネジャーに相談してください。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止および移動の円滑化などのための床、または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- 上記の住宅改修に付帯して必要な住宅改修など
このように介護保険サービスはいろいろな活用法があります。在宅介護の際は主介護者の家族に負担が集中しますので、介護保険サービスを利用しながら心身の介護負担を軽減することがとても大切です。介護サービスをうまく利用することでストレスを軽減しましょう。
介護保険サービスの負担を軽くする制度
次に、利用するうえで大事な費用負担の軽減についての制度を紹介します。
介護保険利用者負担の軽減制度の具体的な内容や、実際の費用の額については個人差及び各行政の制度下によりますので、利用時は必ずお住まいの地域の介護保険課にご確認ください。
では、共通制度についてご紹介しましょう。
高額介護サービス費
月々の介護サービスの定率負担(1割~3割)の合計額について、所得に応じて設定された上限額を超えた場合に、申請により超えた額が支給される制度です。
世帯単位および個人単位で設定されている、高額介護サービス費での1ヶ月の利用者負担上限額を超えた場合に、その超える額が高額介護サービス費として保険給付が行われます。
限度額適用認定証が必要な場合は国保の場合は市町村の窓口、社保の場合は各健保組合、協会けんぽで発行してくれます。
高額医療・高額介護合算療養費制度
医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。
医療保険と介護保険の1年間(8月1日から翌年7月31日)の自己負担合計額が、自己負担限度額(世帯の年間限度額)を超える場合に、当該合計額から限度額を超えた額が支給されます。
支給額は医療・介護のそれぞれの比率で按分し、医療保険からは「高額介護合算療養費」、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。
高額介護サービス費と同じく、国保は市町村の窓口、社保は各健保組合・協会けんぽで申請します。一度申請すれば毎年する必要はありません。
尚、マイナンバーカードで介護保険に登録及び医療機関をマイナカードで受診している場合は申請の必要はありません。
詳細は住居地の介護保険課の窓口で確認するようにしてください。
特定入所者介護サービス費
介護保険施設へ入所(入院)及び短期入所した場合、食費と居住費が原則自己負担となります。
ただし、所得の低い方(市民税世帯非課税の方)には、食費と居住費について「特定入所者介護サービス費」が支給され、負担が軽減されます。
●介護保険負担限度額認定申請書
●預貯金等の額を確認できる書類(本人及び配偶者の預金通帳、有価証券等の写し)
●同意書
を用意して、介護保険課の窓口で申請します。
<参考>利用者負担段階と適用区分
| 利用者負担段階 | 適用区分 | 預貯金等の状況 | |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市民税非課税の方で、本人及び配偶者の預貯金等が一定以下の方 | 単身:1,000万円以下夫婦:2,000万円以下 | |
| 第2段階 | 世帯全員(世帯を分離している配偶者を含)が 市民税非課税の方で、 本人及び配偶者の 預貯金等が一定以下の方 | 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金額の年額が80万円以下の方 | 単身:650万円以下夫婦:1,650万円以下 |
| 第3段階(1) | 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金額の年額が80万円超120万円以下の方 | 単身:550万円以下夫婦:1,550万円以下 | |
| 第3段階(2) | 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金額の年額が120万円超の方 | 単身:500万円以下夫婦:1,500万円以下 | |
対象施設は以下になります。
●介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
●介護保健施設サービス(介護老人保健施設)
●介護医療院サービス(介護医療院)
●短期入所生活介護(ショートステイ)
社会福祉法人などによる利用者負担軽減制度
低所得で生計が困難である方や生活保護を受給されている方に、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とした制度です。
申請の方法は、社会福祉法人の事業者からの申し出により、住居地の市町村が軽減を決定後、確認証が発行されます。
既述のとおり、高額介護サービス費は定率負担のみが軽減対象となり、特定入所者介護サービス費は食費や居住費などの滞在費に対してのみが軽減対象であるのに対し、社会福祉法人などによる利用者負担軽減制度は定率負担・食費・居住費のすべてを対象に軽減されます。
ただし、利用できる施設は社会福祉法人が運営する福祉系の介護老人福祉施設、短期入所生活介護である必要があり、医療系の施設は軽減対象になりません。
その他生計困難者等に対する、利用者負担額軽減事業の実施状況や独自の実施については市区町村によって異なる場合がありますので、住居所在地の介護保険課におたずねの上、確認してください。
尚、既述した負担軽減のための申請は、各市町村の条件を満たした場合ですので、誰でも申請すれば自動的に給付されるわけではありません。含めて、ケアマネジャーをはじめ専門職及び介護保険課の窓口で確認しましょう。